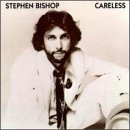2月19日(土)
まさか自分が「やおい」の世界に接するなどとは、つい最近まで考えもしなかった。
とはいえ、私が「やおい」の愛好者になったわけではない。本日開かれた、第2回COEジェンダー英語圏2004年度大会「セクシュアリティの地平――いま見る・読む・感じる表象批評の冒険」 を聴きに行ったのだ。プログラムは以下の通り:
【第一部】講演会
【第二部】研究発表会
Goth・「やおい」・Vamp という取り合わせにクラッときたが、未知の世界をその道の専門家が語ってくれるのだから、自分で勉強するテマが省けて嬉しい。小谷真理という有名人が講演することと、テーマがテーマだけに(?)大講義室は初めから大入りだった。しかも、聴講者はほとんど女性で、男性は1割以下――いや、5分ぐらい――だった。ジェンダーに関わる問題の重要性が、男たちのあいだでは不当に過小評価されているのを感じる。ジェンダー・ジャスティスを求める闘いは、ジェンダー・マイノリティーだけのために闘われるものではないのですよ。
小谷講演は、映画における Goth の表象を現在から遡るかたちで通時的に検証していた。Goth は悪魔的であると同時に堕天使のイメージを体現しており、悪は悪でも単なる悪ではない、いわゆる「善」に対するある種のアンチテーゼとして機能しており、それが映画 Matrixで頂点に達すると同時に善悪が逆転した――みたいな感じだったと思うのですが……。マリリン・マンソンが自らを "anti-Christ hero" と位置付けているという例の紹介は、非常に解りやすかった。その意味では Goth は、ある種の文化的な抵抗であり、[真性]Goth のなかには、単なるコスプレと自らとの間に一線を引く傾向も見られるらしい。
溝口発表が、今回の大会のなかで一番面白かった。このシンポジウムで唯一配付資料がなかったので、自分がとったメモを元に内容をまとめてみたい。
「ホモフォビックなホモはレズビアンを生むか?」というタイトルの意味は次のような感じ。美少年Aがレイプまがいの方法で自分の愛を美少年Bに告白すると、美少年Bは「ホモはイヤだ!」みたいな感じで一旦は拒絶する。しかし、やがて美少年Bは美少年Aの愛を受け入れホモエロティックな欲望の世界へ足を踏み入れる――これが、「やおい」の一般的な(古典的な)フォーマットというかフォーミュラらしい(この部分が「ホモフォビックなホモ」)。発表者である溝口氏は、こうした「やおい」作品を繰り返し受容することを通じて、自身のレズビアン・アイデンティティーを形成していったという個人史を梃子にして、「やおい」とレズビアン・アイデンティティーとの関係を探究している(この部分が「レズビアンを生むか?」)。今回の発表は、現在準備している博士論文の一部だとか。
この調子で全部文章化していくと、長文になってキリがないので、会場でとったメモをそのまま再現すると、こんな感じ:
日時:2005年2月19日(土)13:30〜17:45
男である私は、お茶の水女子大の構内に入る時は、いつも妙な緊張感をおぼえる。小中などの共学の附属学校が併設されており、男性の教職員もいるわけだから、この緊張感は、単なる自意識過剰以外のなにものでもないのだが、自分が怪しい者でないことを殊更にアピールするために、自ら守衛に歩み寄り「理学部3号館7階大講義室へはどう行ったら良いでしょうか?」などと、すでに確認済みの会場の位置をわざわざ尋ねたりするチキン・ハートぶりだ。
第1部13:30〜15:00/第2部15:15〜17:45(懇親会18:00〜19:00)
場所:お茶の水女子大学 理学部3号館7階大講義室
・小谷真理(SF&ファンタジー評論家)
「テクノゴシック論」
・溝口彰子(国立フィルムセンター客員研究員/COE客員研究員)
「ホモフォビックなホモはレズビアンを生むか?――ヤオイのファンタジーと『現実』」
石井達朗(慶應義塾大学)コメンテーター
・山口菜穂子(お茶大(院)、COE-RA)
「トランスアトランティック“ヴァンプ”――アメリカ映画黎明期における性の地政学」
斉藤綾子(明治学院大学)コメンテーター
司会/竹村和子(COE事業推進者)
まず、メモのなかの「*******」は伏せ字ではなく、判読不明の部分です。自分で書いときながらおハズカシい。ゆっくり書けば、ワリと読める字なのですが……。次に、このメモには、私の解釈に誘導された記述や、私の見識不足に伴う事実誤認・誤解も含まれていると思うので、溝口さんの発表の内容と一致しない部分がある惧れがあります。そのつもりで参照して下さい。
今回一番シビレたのは、レズビアンの多様性に関する次のような指摘だ。「女性の同性愛者も、同性愛経験の全くない主婦もレズビアンたりうる」、レズビアンとは「レズビアンの名の下に活動することを決意した人(J. Butler )」である。このテーゼは論理的に敷衍すれば「ヘテロセクシュアルな男ですらレズビアン・アイデンティティーをもちうる」ということになるのではないか! ジェンダー・アイデンティティーを本質主義から解放する、この認識の原形──とはいえ私が無知なだけで、もっと遡って先駆的な例を発見できるかもしれないが──は、Caroll Smith-Rosenberg, "The Female World of Love and Ritual: Relations Between Women in Nineteenth-Century America", Signs: A Journal of Women in Culture and Society Vol.1 No.1 (1975) (Judith Butler & Joan W. Scott eds., Feminists Theorize the Political (New York: Routledge, 1992)に再録)で早くも表明され、それ以降展開され、今や常識に属するものと言えるだろう――ただし、悲しいことに現実には、あの大会議室の中に同席した者と、あの同席者と志をともにする者にとっての、通用範囲の限定された「常識」に過ぎないのかもしれない。この認識が世の人びとに遍く共有される日が来るならば、それは、ジェンダー・アイデンティティーにより何ぴとも差別されない世界の到来であり、ひとつの革命なのだが……。
実は、私はサブカルに関してはズブの素人で、「BL」「ゆりもの」、それどころか「やおい」すら良く知らなかったのです。発表の過程で、具体例として紹介されたいくつかの「やおい」作品の中身に、ハッキリ言ってオドロイタよ私は。「そのまんまじゃないか」と心のなかで声にならないツッコミを入れましたよ。
山口発表は、映画黎明期におけるアメリカ映画 A Fool There Was に見られる「ヴァンプ」"Vamp"("vampire" に由来する言葉で、「妖婦」の意味)の表象についてであった。発表自体は面白かったが、前のふたりの発表が長引いてしまったせいで、発表時間が大幅に短縮されてしまって残念だった。ヴァンプを演じる女優 Theda Bara は、アメリカ出身であるにもかかわらず、サハラ生まれでフランス経由でアメリカへわたって来た、という架空のアイデンティティで売り出されていた点は、オリエンタリズムの典型だろう。他には、「ヴァンプ」と移民の売春問題や白人奴隷の問題との関係などが指摘されていた。
この会全体の感想としては――濃かったなぁ、しかし。
 |
2月24日(木)
ヤコブ・ビリング(中田和子[訳])『児童性愛者―ペドファイル』(解放出版社、2004年)を読んだ。どうも最近「下ネタ」づいている。ジェンダーにかかわるイシューは、近代以降の社会を考える上で鍵となるのです。
この本は、デンマークの若手ジャーナリストが、デンマーク児童性愛者協会という法的に認められたペドフィリア(=児童性愛[者])団体に潜入取材したテレビ・ドキュメンタリー番組『デンマークの児童性愛者』の取材過程を一人称で書いた本である。文体は平易で非常に読みやすく、その気になれば数時間で読めそうだ。推理小説のようなテイストをもった本でもある。梁石日(ヤン・ソギル)の手による解説も付いているが、これは期待した程ではなかった。日本社会から排除されると同時に統合されてきたマージナルな出自をもち、そのことについて繰り返し問うてきた彼にしては、一般的なアティチュードに感じる。
前まえからペドフィリアの問題には興味があった。念のために断っておくが、私は、児童性愛行為をはっきりと違法と認識し、道義的にも許されない、処罰すべきものと考えており、擁護する気も毛頭ない。また、私が興味をもつのは、「児童性愛」という問題であり「児童」ではない。ここでいう「問題」という言葉の含意は、児童性愛は problem であると同時に issue である、という認識である。とはいえ、ある種の誤解を怖れて、この本を手に取ることを永らくためらい、手に取った後も電車の中で読むことを控えている自分の態度や行動を顧みるにつけても、こうした問題が problem として恐怖をあおるかたちで扱われても issue として扱うことが避けられていることを感じる。
まず、「児童性愛」という用語についてだが、本のなかでも「編集部註」で言及されているが、従来「小児性愛」と訳されてきた「ペドフィリア」あるいは「ペドファイル」を、「著者がルポしている実態からして『小児』では範囲がせますぎ」、「子どもへの虐待関連法令で使用されているのは『児童』」であることから、この本では「児童性愛」と訳している(p. 243)。本の内容・法令という理由以外にも、ペドフィリアを一面化せずその多様性を読み取るという観点からも「児童性愛」という訳は一般的に支持できる。
この本の著者の問題関心を一文でまとめると、「憲法に〈結社の自由〉が謳われているからといって違法行為の扇動が公共の建物で行われることが妥当か否か?」(p. 238)ということになる。この本では、デンマーク児童性愛者協会は、アーレフェルト通りの公民館で会合を開いた後、公民館長からの開場使用拒否の手紙が渡される(p.76)。デンマーク児童性愛者協会は、〈結社の自由〉により護られている公認の団体ではあるものの、社会的な風当たりは強く、公的な施設からも閉め出されている。
本の中に登場するペドフィリアたちは、子供たちと性行為することを、「子どもの側から、自分もセックスをしたいという "自発的な働きかけ"」(p. 112)があるという認識によって正当化している。これには呆れてモノが言えない。法律で禁止された行為の正当性の根拠が、自分自身の身勝手な認識とは。
この本に登場するペドフィリアたちは、一見するとごく普通の市民で、失業者からナショナル・アーカイヴの所長まで多様である。さらに、「デンマーク成人中、子どもにのみ性欲を抱く指向がある者は一万人以上と推定する専門家もいます」(p. 232)とのこと。また、彼らの性的選好は、ペドフィリアという共通性はあるものの、男児か女児か両方か、どの年齢が好きかなど、その内実は多様である。「ペドフィリア」を全体化する外皮の背後にある個別性・多様性を具体的に描き出すためには、潜入取材という方法は効を奏していると思う。ペドフィリアの実態を知る情報源として、このような著作が翻訳される意義は大きい。入手困難な情報を自分で行って取ってきたこの本の著者に対して純粋な敬意を表したいと思う。
しかしながら、敬意を表するからこそ感じる物足りなさや違和感もある。
例えば、ひとつ目は、インタヴュー中の法務大臣の返答とこれに対するこの本の著者の同僚記者の反応が多少気になる:
彼ら/彼女らが実際に児童性愛行為に至った場合には、直ちに逮捕すればよいし、子供たちを違法行為から護る努力はすべきだろう。このことには全く異論はない。ただし、この本に出てくる実行行為を伴うペドファイルを一方の極に置き、たった今私が仮構した「やらずのペドフィリア」をもう一方の極に置くスペクトラムを想定すると、違法/合法の境界線はどこになるのかを議論しておく必要があるのではないか。デンマーク児童性愛者協会の場合は、会の掲げる〈成人と子どもとの間の性的関係に対する偏見を取り除くこと〉という目標(p. 227)を思想・信条と捉えるか、「犯罪行為の扇動」と捉えるか――ここが issue となるはずだが、この本では論じられていない。デンマーク児童性愛者協会という団体は、このスペクトラムのどこに位置するだろうか。
私がこのようなことを言うのは、別にペドフィリアを弁護するためではない。こういう特殊な性質の団体への取締を契機に、思想・信条への統制が普遍化することを危惧しているからだ。
次は、この本の著者による認識のフレームの操作が気になるという点である。例えば、著者の日常生活が次のように挿入されることで、著者の「正常性」と児童性愛者の「異常性」が強調され、読者は二項対立の図式に動員されそうになる:
「ぼくは、娘を一方の手に、恋人をもう片方の手に取り、息子は肩に乗せていた。デンマーク郵政省の自転車レースのラストパートを見る予定だった。[……]ぼくにとっては、家族と一緒にすごすのは、いま関わっている仕事を忘れるには最良の方法だった。」(p. 168)
ところで、本から離れると、「性犯罪者の再犯防止問題で警察庁は23日、13歳未満の子供を被害者とする「暴力的性犯罪」について、昨年1年間に摘発した容疑者の前歴状況を調べるとともに、1982年から97年までの強姦(ごうかん)容疑者の再犯状況についての追跡調査を行うことを決めた」(共同通信、2005年2月23日)とのこと。このような性犯罪者を公開・監視する措置の実施も、巷間噂されている。「再犯率の高さ」を理由に一度でも性犯罪を犯した人物を公開・監視することを主張する人は、2回以上の殺人や銀行強盗を行ったすべての再犯者も公開・監視することを主張しなければならない。再犯「率」の高さどころか、現に再犯しているわけだから。前者の主張は今にも通りそうだが、後者は通らないだろう。でも、ある友人に話したら「じゃ、それでいい」とアッサリ言われてしまった。私個人としては、「違法行為をやった人はさっさと捕まえ、違法行為の防止に徹底的に努める」という原則で充分ではないかと思うが、子をもつ親は心の底から不安なんだろうな。それも解る。
ヤコブ・ビリング(中田和子[訳])『児童性愛者―ペドファイル』(解放出版社、2004年)は、デンマーク児童性愛者協会という個別の対象を扱った作品であるから、ここで紹介されるペドフィリアたちの生態を普遍的なものであると捉えることには留保が必要だ。日本のペドフィリアの場合はどうだろう。
「[……]でも私の理解している範囲では、児童性愛の指向があるからといって、必ずしも実行行為におよばないのではありませんか」
この同僚記者の「実行せずに性的指向を持つことはできない」という認識――この本の著者も共有していると推測する――は、この本に出てくるペドフィリアには有効である。ここまではよいが、この認識そのものの妥当性には限界があるかもしれない。少し敷衍して考えてみたい。児童性愛行為を全く実行しない、例えば児童性愛的内容のアニメーションやコミック――つまり、実在の児童の虐待を伴わない作品――の継続的愛好を通じて児童性愛的指向を保持するペドフィリアが存在する可能性はある(実際に存在していると考えて間違いないだろう)。実行行為におよばないペドフィリアたちが、共通の指向をもつものとして結社し、公民館で集会を開いたとき、彼らを閉め出すことができるのだろうか。もし可能であるならば、それは思想・信条に基づく差別ではないか。
「どのようにして、実行せずに性的指向を持つことができるんですか?」(p. 228)
[※児童性愛者の集会への潜入後の、この本の著者の自宅での彼と恋人のやりとり]
私は、以前の日記でマイケル・ムーアの一連の作品群を諷刺と捉え、その[戦略的]偏向を支持し愛好すると書いた。しかし、今回の本は潜入取材という手法を採る以上、ムーアと同じようにはいかないのではないか。もう少し的確に言い直せば、もったいないのではないか。他の方法では決して得られない豊穰なディテイルを伴った希有な情報によって再構成された「場」に読者を招待し追体験させることが、潜入取材モノの醍醐味だと思う。しかし、この本については、著者自身がナラティヴをコントロールし過ぎていて、当の読者が「潜入」することを阻んでしまっているのではないか。もう少し読者に判断を任せるオープンな作品に書き上げたほうが良かったのではないかと感じる。著者に感情移入させて物語に引き込むことを狙ったと考えることもできるが、もしそうなら、私に関してはその目論見は失敗している。著者の物語が語られれば語られる程、私はそれをヤコブ・ビリングの物語として外から読んでしまうのだ。
「随分かかったわね。いい集まりだった?」
「うん」
彼女に背を向けて座っていたぼくに、彼女は近づいて来た。
「まぁ、どうしたの? 泣いてるじゃない」
「そう?」
「そうよ、ほら、こっちにいらっしゃい……」(p. 100)
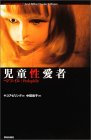
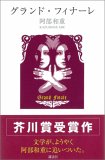
2月25日(金)
今日、自分のサイトの 700 ヒット目と読書会のページの 400 ヒット目を自ら踏んでしまい、チョットもったいない気がした。誰か他の訪問者の方に踏んでほしかった。
2月28日(月)
あまりCDを買わないので、すでに所有しているものを繰り返し聴くことが多い。
最近、Stephen Bishop, Careless(MCA, 1976)(※日本版はユニバーサルインターナショナルから発売)を聴き直した。すべての曲が素晴らしいが、なかでも "Madge" という曲に改めて聴き入ってしまった。ギターの弾き語りというシンプルなスタイルの曲にもかかわらず、映画を一本観たような充足感がある。恐るべき ballade だ(日本語の「バラード」ではない)。
* * *
Madge
Stephen Bishop
It was 1927
I built a lot of buildings
We ate in the finest restaurants
It seems so long since I've remembered
Like a storm in a teacup
They call this place "Sunnyside"
Madge, she's probably married now
But I got my TV turned up loud
Like a storm in a teacup
Had the world at my feet
A pretty girl on each arm
My family was so proud of me
Tore half of 'em down
One by one
They all crumbled just like me
But like a storm in a teacup
Like a smile sent down from heaven
Madge, I loved you then
and I love you now
Had the wealthiest friends
Most of them are gone now
No one left to say, "I knew you when"
The girl I used to know
She never saw any of my money
But she watched it come and go
Like a smile sent down from heaven
Madge I loved you then
And I love you now
But I ain't seen the sun
In a long, long time
And my hands don't seem too steady now
But they're still holding onto you
In a nice white house
And me I just sit here in my room
Quiet as a mouse
I'm not going to hear myself retreat
If only I'd have kept her
I'd have stayed on my feet
Like a smile sent down from heaven
Madge I loved you then and I love you now...